
日本では、厚生労働省が食品衛生法に基づいて農作物等の残留基準を設定しています。
この残留基準を超えるような農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)が残留している農産物等は、食品衛生法に基づき販売禁止等の措置がとられることにより、農作物等の安全が確保されています。
日本を含め全世界で食用農産物に使用される農薬や動物薬、飼料添加物などは約700以上ありますが、そのうち日本で残留基準が設定されている農薬等は283成分(平成17年11月現在)に過ぎません。
こうしたことから、厚生労働省は平成15年(2003年)に食品衛生法を改正し、基準が設定されていない農薬等が、一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)に、3年以内に移行することとしました。
この制度は、平成17年11月29日に告示され、平成18年5月29日から施行されています。 |
○従来の規制(ネガティブリスト制度と呼ばれています)
この規制は、原則、自由の枠組みの中で、残留が認められないものだけをリスト化する方式です。
但し、この制度ではリストに掲載されている農薬であっても基準値設定のない農作物等で検出された場合やリスト外の農薬が検出された場合、規制できないことが問題点でした。
〔従来の制度のイメージ〕 |
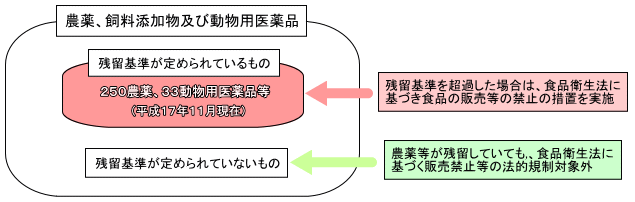
○新たに導入された規制について(ポジティブリスト制度と呼ばれています)
従来の制度の問題点を解決するため、原則、禁止の枠組み中で、認めるものだけをリスト化する方式です。
ポジティブリスト制度においては、約135の農作物分類と799農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)について残留基準が設定され、この残留基準を超えて検出された農作物等の販売等が原則禁止されます。
また、リスト外の農薬等が一定量以上検出された農作物等の販売等も原則禁止されます。
〔ポジティブリスト制度のイメージ〕 |
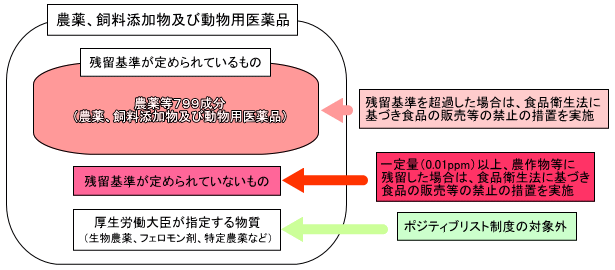
| (参考)ポジティブリスト制度での残留基準設定について |
| (1) |
残留基準が設定されていたもの → 従来の残留基準が適用されています。 |
| (2) |
国際基準(Codex基準)や海外基準、農薬登録保留基準をもとに設定されたもの(暫定基準と呼ばれています) → 新たに暫定基準が設定され、この基準が適用されています。 |
| (3) |
参考とする国際基準等がなく、暫定基準を設定しないもの → 一律基準(0.01ppm)が適用されています。 |
この制度によって、次のような事が想定されます。
流通・販売段階での農産物などは、食品衛生法に基づき規定される残留基準を超えて農薬等成分が検出された場合は、同法第54条に基づき回収命令等の措置がとられます。
そのため、隣接したほ場で他の農作物を対象に他者が使用した農薬が飛散し、自分が生産する農産物等から残留基準を超えて検出された場合も、同様の措置がとられこととなります。
〔農薬飛散のイメージ〕 |
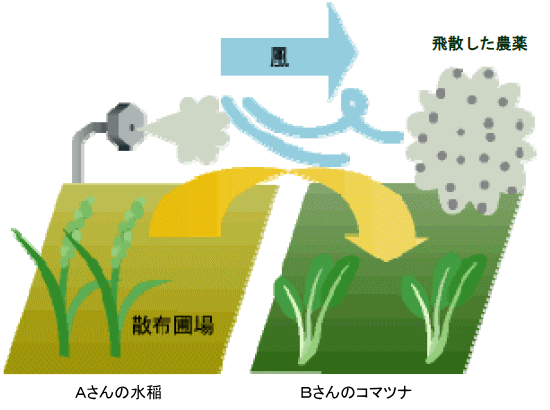 |
出荷されたBさんのコマツナから隣接ほ場で使用された農薬成分が残留基準を超えて検出 |
このようなことが生じないよう、
(1)農薬のラベルに記載してある内容を確認して、農薬を適正に使用する
(2)風が強く農薬が飛散しやすい時に農薬散布をしない
ことはもちろんですが飛散防止対策を実施することが有効です。
具体的な対策としては農林水産省ホームページに対策が紹介されていますので参考にしてください。