

1月18日に、倉吉体育文化会館を会場に、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の初任者研修、及び幼稚園・幼保連携型認定こども園教員、養護教諭、栄養教諭の新規採用者研修の本年度最終回を行いました。
教職をスタートさせたこの一年の実践を互いに発表し合い振り返るとともに、今後の目標設定を行い、最後は、東部教育局の徳高雄一郎局長の「これからの教師に望むこと」と題した講話を聞き、まとめとしました。実践発表と協議、講話をとおして、各自の成果や課題を見つめ直したことにより、達成感をもつとともに、来年度の実践に向けて意欲を新たにされたように思います。
初任者・新採者の振り返りをいくつか紹介します。
- 徳高局長の講話の中で、特に、「これからの教師に望むことは『受け止める、つながる、学び続ける』」という言葉が印象的でした。今後の教員生活において継続的に、この考え方を大切にしていきたいと思いました。困難から逃げず、つながった人とともに受け止めた困難を解決していくことを繰り返し、何を学び続けたいのかを常に自分の中に持っておくことを意識し、教師として成長し続けたいと思います。
- 今回、いろいろな先生方の実践を聞いて、授業での取組や終学活での取組など、具体的な実践をたくさん学ぶことができました。また、解決に向けて悩んでいることには、いろいろな解決の仕方があるのだと気づくことができました。悩んだりうまくいかなかったりした時は、具体的な解決策や小さな活動を考えたり、聞いてみたりしたいです。
- 今回の研修で学ばせていただいた「学び続けるとは、悩み続けること」、「前向きに、丁寧に、ねばり強く」という言葉を思い出し、児童の幸せと自分の成長の種だと心に留め、前向きに努力していきます。
- 初任者研修は終わりましたが、今後も学び続け、自分自身も成長していけるように様々な学びの場に自ら足を運びたいと考えています。
これらの思いが、それぞれの成長につながるように来年度の研修等を検討していきたいと思います。


11月21日、倉吉体育文化会館を会場に、ナラティブ・コミュニケーション教育研究所所長の佐藤敬子氏を講師にお迎えして、「課題を抱える子どもたちへの寄り添い方~コーチングの手法を活かして~」研修を実施しました。それぞれの子どもたちが持っている能力を引き上げるコーチングの手法について、わかりやすく豊富な具体例をもとに、演習を交えて学びました。佐藤先生のエネルギッシュな語り口に引き込まれ、あっという間の研修となりました。
今、子どもたちと保護者をとりまく社会的背景から、人間関係やサインが見えにくくなっており、困難を抱える子どもの保護者もまた、困難を抱えています。
例えば不登校。きっかけと要因はあるが、原因はなく(わからない)、いずれ不登校状態に飽きる時がくるのだそうです。そして、一度目のその時に学校と家庭で支援をすることがポイントなのだそうです。学校の「引き上げるタイミング」と家庭の「押し上げるタイミング」を見極めること、ゴールを共有することが重要で、顔が見える関係での組織的な支援体制を整える必要があります。
コーチングは、相手のやる気や意欲という目に見えない力を引き出しながら、相手の自己解決を図り自己実現をめざすものです。必要とする答えは相手の中にあり、課題の解決は相手にしかできません。そのためには、相手をわかろうとする気持ちが一番大切であり、相手の関心を聴き、存在を認め、変化や行動、姿勢とうい目に見えないものを認めることが重要です。
コーチングには、次のようなスキルが必要となります。
- 「聴く」… 自分の関心より相手の関心を聴く。相手にとって話を聴いてもらいたい人になる。
- 「承認する」… ほめることは大切、さらに大切なのが存在をほめる(認める)こと。変化、行動、姿勢という目に見えないものをほめる。自己肯定感を持たせる。
- 「質問する」… 否定質問より肯定質問、過去(後ろ)より未来(前)の質問がよい。
- 「伝える」… 次の順に伝える (1) 日頃の相手に対する承認の言葉 (2) 相手が納得し問題解決の手立てを自ら考え主体的に行動するための効果的な質問(指導すべき内容) (3) 感謝と期待をこめた言葉
「伝える」ということは、相手が心から納得し、伝え手が期待していた行動を自らとる状態になることです。みなさんは、いかがでしょうか。一方的に「話した」という伝え手の事実のみで終わっていることはありませんか。

11月20日に、関西外国語大学の新井肇教授を講師にお迎えし、【生徒指導】「保護者との関係づくりのための理論と方法」研修を実施しました。教職員が保護者との間によりよい関係を築くために、どのように向き合い、対応するのがよいのか、事例検討等をとおしてその考え方や方法を学ぶ機会としました。
はじめに、児童生徒の問題行動は、大人や社会、教員や学校に対する「問題提起行動」でもあり、困った(行動をする)子は(課題を抱えて)困っている子という視点に立ち、問題行動や不登校が増加している現状を児童生徒の「心の危機」が深刻化しているととらえることが大切と確認しました。
子どもを取り巻く社会状況の急激な変化により、多様な背景をもつ児童生徒が増加している現状を鑑みると、児童生徒のよりよい成長・発達のために、子どもの成長・発達を地域で支えること、そして、学校と家庭・地域との連携が必要なのは明白です。
保護者との関わりにおいて求められる基本姿勢としては、普段から信頼関係を築いておくこと、相手の身になって感じる「共感的理解」に努め、カウンセリング的な姿勢をいかし、言葉の向こうにあるものを理解したり、言葉にならない「ことば」を聴いたりすることがポイントです。また、相手の話をきちんと受け止めるためには、自分の考え方や感じ方のくせを知ることも重要です。
それぞれの事例では、保護者や児童生徒に寄り添って、共感的に心理状態を理解しようとすることを大事にして、どう捉えたらよいか、どう理解し、どう対応したらよいのかを考えました。そして、次のようなことを大事にするとよいとまとめました。
・保護者との信頼関係を築くためには初期対応が肝心
・決めつけや思い込みを取り除く
・子どもの問題をめぐって、教師と保護者が目標を一致させる
・学校のできること、できないことをはっきりさせ、組織的に対応する
・子どもをめぐって協力し合うパートナーとしての関係を築き、保護者の訴えの背後にある思いや願いに気づく
また、保護者との関係づくりにおける留意点として、次の点で自分自身の姿勢を考えることも大切です。
・謙虚な姿勢…時には家へ出向いたり労をねぎらったりしていますか。
・気持ちの受け止め…共感的に聴き、言葉の背景にある気持ちを受け止めていますか。
・正確な事実把握…正確な事実把握、保護者の伝えたい内容の客観的整理をしていますか。
・丁寧な説明…児童生徒への対応について、丁寧にわかりやすく説明していますか。
・組織的な対応…保護者との対応状況を同僚や管理職と一緒に考えていますか。
・目標の確認…その子どもにとって何が大切であるか保護者と共有できていますか。
みなさん、御自身の保護者対応はいかがでしょうか。




11月9日、16日の両日、船上山少年自然の家を会場に、自然体験と集団活動の意義について学ぶ初任者研修を行いました。11月30日にも予定しており、3日間で全ての校種の初任者が受講します。様々な校種の初任者が参加しましたが、同じ目的をもって体験活動や集団活動を行うことにより、自ずとコミュニケーションが生まれ、校種を超えた初任者同士のつながりを深めることができました。
活動の一つとして、野外炊飯でカレー作りを行いました。役割分担をして自分の役割を果たすことはもちろん、周りを見ながら自分のできることを考えて行動する初任者の姿も多く見られました。はじめは硬かった表情も、グループでの活動を重ねる度に、徐々に和らぎ、笑顔で関わり合いながら活動する姿がとても印象的でした。また、様々なレクリエーション体験で次々にペアやグループをかえる中で、拍手や歓声をあげて満面の笑みを浮かべながら交流を深めました。活動のはじめと終わりには、ビーイングという手法を使って、グループごとに目標設定や振り返りを行い、体験活動や人間関係づくりをとおした学びや気づきを共有しました。
初任者の振り返りをいくつか紹介します。
・今回のことをとおして、児童が繋がり合い、仲間づくりをすることができるしかけを教師側がつくっていくべきだと感じた。少しのしかけがあるだけで、児童はワクワクし「もっと知りたい!」という意欲が湧くのだと、今回の体験活動で実感することができた。
・何事も楽しく活動をして終わりではなく、どうしてこの活動をするかというはっきりとしたねらいをきちんと持って毎時間の授業や活動に取り組みます。また、私のもつねらいを子どもたちと共有したうえで、子どもたちが何を学ぶかを考えながら授業をしていけるように取り組みます。
・レクリエーションやカレーづくり、ビーイングによる目標設定と振り返りなど、たくさんの活動をとおして大人でも仲間という意識が芽生え、一緒に熱中して取り組むことができた。子どもは仲間づくりにおいては大人よりも円滑に、上手にしていると感じる。仲間をつくるのがゴールではなく、その場限りの関係ではなく、今後も何かしらのコネクションを持つという意味での仲間づくりをしていく必要がある。来年の3月までに学級内でお互いが居心地のよい仲間となれるよう、担任として支えていきたい。
中本所長の講話にあったように、参加者一人一人が学びを生かし、決して体験のやりっぱなしにせず、体験したことが学びにつながるような働きかけを意識し、児童生徒の指導、支援に取り組んでいくことを期待します。
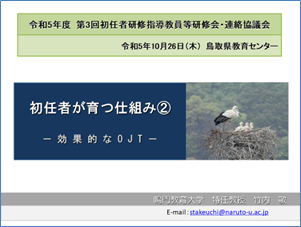
第2回の研修会・連絡協議会に引き続き、10月26日に「初任者が育つ仕組み(2)~効果的なOJT~」というテーマで、鳴門教育大学の竹内敏特任教授に御講義いただきました。
校内で初任者及び若手教員の育成を図るためには、ミドルとベテランとをコーディネートする役割の存在や学校全体で関わり共に育てていくという意識が必要です。また、学級経営や保護者対応、職場の人間関係等に悩む初任者に対して、メンタル面でのサポート、つまりレジリエンス(困難をしなやかに乗り越え回復する力)を高めることが大切であり、同僚の協働的な支援がレジリエンスを高めることにつながります。
この研修で一番考えを深めたかった内容は、これからの教師の学びです。それは、「『教え方』を教える」という考え方から脱却し、「『学び方』を教える」という考えにシフトしていくということです。「学び方」を教えるためにどのような実践が考えられるか、グループで協議し、全体で考えを共有しました。各参加者の振り返りには、初任者への関わり方や指導の仕方について省みて、これからの校内での人材育成における重要なヒントを得て今後の取組への意欲を新たにするコメントが多く見られました。一部を紹介します。
【振り返りから】
- 初任者の立場に立ち、困り感を共有できるような研修を組んでいきたい。
- 初任者のレジリエンスを高める方策をじっくり考えてみたい。そのためにも会話の機会を増やし、初任者への問いかけを工夫していきたい。自分が今までどう学んできたのかを初任者に自己開示してみたい。また、学校の先輩たちはどう学んでいるかを初任者とともに学べる機会をつくってみたい。
- 「学び方」を一緒に考えていけたらと思った。問いかけ考えさせ、新たな視点に気づかせていけるようにしていきたい。
- 初任者=教えられる立場ではなく、自分で学ぶ姿勢を育成することが初任者の成長につながると思った。
- 昔と違って授業のノウハウもネットを探せばたくさん出てくる時代において、表面上の指導は効果がなく、これまでの経験で得た生の感覚や出来事(エピソード、失敗談)などをざっくばらんに話すことが、何よりの生きた指導になると感じた。そして、最後は指導力とともに人間として成長できる1年間であることを念頭に置いて指導していきたい。
- 「省察が自分を成長させること」は、そのとおりだと改めて感じた。それを初任者にはもちろん、自分自身にも生かしていきたい。