平成13年2月
環境政策課
「鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例」第8条第1項の規定に基づき、平成11年度における環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策及び平成12年度の施策を環境白書としてとりまとめたものである。
併せて、鳥取県環境基本計画に設定された目標値に対する進捗状況を盛り込んでいる。 |
表紙・目次(PDFファイル 520キロバイト)
本文1 (PDFファイル 1,839キロバイト)
本文2 (PDFファイル 1,980キロバイト)
本文3 (PDFファイル 1,605キロバイト)
本文4 (PDFファイル 1,196キロバイト)
本文5 (PDFファイル 1,137キロバイト)
資料編 (PDFファイル 1,857キロバイト)
平成12年版鳥取県環境白書の概要
第1章 本県の環境行政の動向と最近の環境問題
[環境行政の動向]
近年、身近な環境問題に加えて、地球温暖化などの人類共通の生存基盤に関わる重要な問題が顕在化している。
これらに対処するため、「鳥取県環境基本計画」を策定し、7つの重点プロジェクトと18の数値目標を定め、達成に向けて推進に努めている。
県の全機関では、「環境にやさしい県庁率先行動計画」を推進している。さらに、平成11年6月の知事のキックオフ宣言を受け、本庁知事部局の事務・事業を対象にISO14001認証取得に向け準備を進め、平成12年12月に認証取得した。
大規模開発事業について環境配慮を進めるため制定した「鳥取県環境影響評価条例」に基づき、平成11年度は「鳥取県環境影響審査会」を設置し、「鳥取県環境影響評価技術指針」を策定した。これによって、影響評価及び事後調査が適正に行われる体制が整った。
本年4月には「鳥取環境大学」が開学するほか、平成14年の開設を目指し「鳥取県衛生環境研究所」の整備を進めている。
[最近の環境問題]
ダイオキシン類、環境ホルモン等化学物質による環境汚染などに県民の関心が高まっており、これらについて調査を行った結果、県内において特に高い数値は認められなかった。
また、化学物質による環境問題の新たな対策として、平成11年7月にPRTR(環境汚染化学物質排出移動登録)法が制定された。今後、同法の円滑な施行に向け、事業者への周知を図る予定。
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会を、資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される「循環型社会」に変えていくことが求められている。県では、「ごみ処理の広域化計画」の推進を図るとともに、「鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例」を平成12年3月に制定した。
第2章 平成11年度における環境の状況
[生活環境の状況]
1 大気環境
大気汚染に係る環境基準物質の平成11年度測定結果は、光化学オキシダントを除く各測定項目について、各測定局とも環境基準値を大幅に下回っており、経年的に見ても横這いの状況である。光化学オキシダントについては、全地点で昼間の1時間値が一時的に環境基準を超える時間があったが、緊急時の措置基準を超えることはなかった。
自動車騒音については、交通環境影響調査を実施した県内10地点のうち、道路近傍で環境基準を昼夜とも6地点が達成、後背地では昼夜とも全地点が達成していた。
一般環境の騒音については、調査した県内12地点のうち環境基準を昼夜とも11地点が達成していた。
2 水環境
公共用水域における平成11年度の環境基準達成状況(BOD又はCOD)は、三大河川(千代川、天神川、日野川)で92.9%、湖沼で9.1%、海域は 81.3%となっている。二級河川の水質は平成10年度とほぼ同程度である。都市河川については全体として汚濁している。
いずれの湖沼も、富栄養化が進行した状態となっている。
地下水は、調査した37地点のいずれも環境基準に適合していた。
3 廃棄物
一般廃棄物は、平成10年度のゴミ排出量は約21.5万トンで、平成元年をピークに少しづつ減少傾向であったものが、やや増加している。平成10年度末の一般廃棄物最終処分場の残余容量は約79万m3となっている。
産業廃棄物は、平成10年度の産業廃棄物発生量は195万6千トン、平成17年には平成10年の1.06倍の208万1千トンが見込まれている。県内の最終処分場の残余容量が少ないことから、早急に処理施設を確保していくことが必要となっている。
4 環境汚染化学物質
ダイオキシン類濃度については、県が平成11年度に実施した一般環境中の測定結果では、ダイオキシン類対策特別措置法に定める環境基準値を大幅に下回っていた。
[自然環境の状況]
鳥取県の森林面積は平成11年で25万8,688haであり、ほぼ横這いの水準で推移しているが、わずかに減少していく傾向にある。農地は、都市化の進展等により次第に減少し、その一方で耕作放棄地が漸増傾向にある。自然海岸の残存率は48.7%となっている。
鳥取県自然環境保全条例に基づき、「自然環境保全地域」を平成11年度までに、12地域指定し、その保全を図っている。
貴重な野生鳥獣を保護するために21カ所、34,162haの鳥獣保護区を設定している。
[快適環境の状況]
本県の自然は、県民のみならず多くの人々にとって貴重な自然とのふれあいの場となっている。県民一人当たりの都市公園の面積は11.2平方メートルで、全国平均の7.9平方メートルよりも広くなっている。
[資源利用の状況]
本県の石油製品の使用量は、平成11年度は106万1,239klとなっている。これは平成2年当時に比べて11.7%の増加である。電力需要は、平成 11年度で34.5億kwhとなっている。平成2年度当時に比べて37.3%の増となっており、引き続き増加傾向にある。ガスの販売量は、平成11年度で、都市ガスは1,728.3億キロカロリー(723百万メガジュール)、プロパンガスは57,486トンとなっており、平成2年当時と比べると、それぞれ21.7%増、18.9%増となっている。
[地球環境の状況]
地球環境問題は、国の枠を越えた広域的な取組を必要とする。本県では、「とっとりアジェンダ21」の普及啓発のほか、環日本海諸国の環境分野での交流・協力を進めている。
| 第2部 平成11年度において講じた環境の保全及び創造に関する施策 |
環境基本計画では、計画推進上重要性が高く数値化できる指標を目標値として整理している。
この目標値に対する達成状況は以下のとおりである。
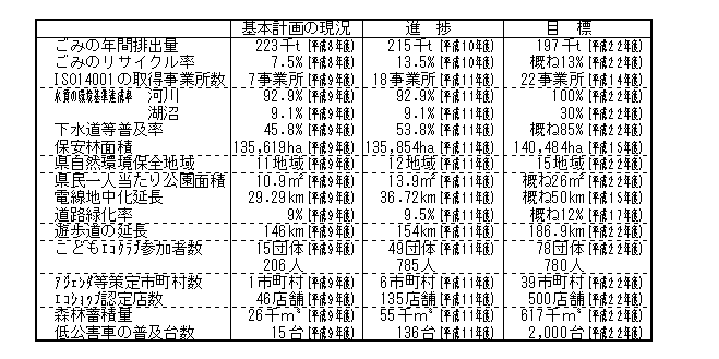
第3部 平成12年度の環境の保全及び創造に関する施策
|
環境基本計画の柱に沿って、施策の推進に努める。
1 循環を基調とする経済社会システムの実現
・ 循環型社会推進本部の設置による全庁的推進と個別対策の実施
4つのR推進、建設副産物リサイクル、家畜排泄物の適正処理、再利用
下水道汚泥の減量化・再利用、工業団地のゼロ・エミッション調査
・ 環境汚染化学物質の適正管理
環境ホルモン汚染実態調査及びダイオキシン類調査の実施と公表
PRTR法の周知
2 自然と人間との共生の確保
・ 森林、農地、水辺地の持つ環境保全機能の確保
保安林の整備管理、人工林及び天然林の整備
棚田地域の保全と活動支援、農薬及び化学肥料の5割削減地域育成
磯場環境改善調査
・ 多様な自然環境の保全と生物多様性の確保
自然環境保全地域や緑地環境保全地域の新規指定調査、
身近な生きものが棲むふるさとづくり事業、野生生物生息実態調査
3 快適な環境の保全と創造
・ 自然環境と調和した生活空間の創造
電線共同溝や自転車道の整備
フォレストタウン(木の町づくり)や環境共生モデル住宅団地整備
4 すべての主体の参加による行動
・ 自主的活動の推進
国際環境規格認証取得モデル企業育成支援、リサイクルフェアの開催
エコ普及活動への支援
・ 環境教育、学習の推進
環境教育・学習指導者研修会、交流会の実施
環境教育用資材、プログラムの整備、小学校低学年用副読本作成
環境パトロール活動発表会開催
5 地球環境保全に向けた活動の推進と国際交流
・ 温暖化防止対策
新エネルギービジョン策定、鳥取県版環境家計簿の普及、コツコツ家族大賞の表彰
エコキャラバン(連続実践講座)の実施、ノーマイカー運動の展開
・ オゾン層保護対策及び酸性雨防止対策の推進
鳥取県フロン回収等推進協議会による回収状況の把握及び促進
紫外線量の実態調査
酸性雨、酸性雪調査
生活環境部・農林水産部合同先進事例調査
・ 環日本海諸国との連携強化と協力
環日本海圏地方政府環境フォーラム、子ども環境サミットの開催
環境分野における江原道との研究者相互派遣、吉林省研究員受入
鳥取県、島根県、吉林省による松花湖富栄養化調査の共同実施
6 共通的基盤的施策の推進
鳥取環境大学の建設工事及び開学準備
衛生環境研究所の建設
鳥取県環境情報ホームページ作成
環境に関する監視体制の整備と調査研究の実施